お店で子供が気に入っていたので、買ってあげたおもちゃ。なぜか家に帰ってきたら、子供が全然遊んでくれない…。
そんな経験ありませんか?忙しい毎日の中で、せっかく選んだおもちゃを見向きもしてくれないのは、ちょっと悲しいですよね。

あんなに泣いて欲しがったから買ったのに、家に帰ってきたら見向きもしな〜い!!



子供のあるあるですよね!突っ込みたくなります。笑。
でも大丈夫です!そのおもちゃ、ちょっとした工夫で子供の新しいお気に入りに変わるかもしれません。
この記事では、子供がおもちゃで遊ばない理由と、それを楽しく遊べるようにするコツをご紹介します。
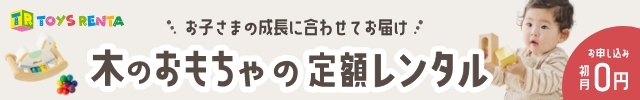
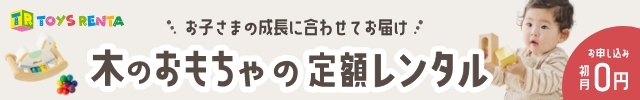
子供がおもちゃで遊ばない心理とは?
まず、子供がおもちゃで遊ばない理由を知ることが大切です。こんな心理が関係しているかもしれません。
- おもちゃの使い方が分からない
特に新しいおもちゃや複雑な仕組みのものは、どうやって遊ぶのかピンとこないことがあります。 - 興味が他に移っている
子供は日々成長し、興味の対象もどんどん変わります。買ったときには大好きだったキャラクターも、時間が経つと飽きてしまうことも。
それこそ、お店では魅力的に思ったおもちゃが、家に帰ってきたタイミングでは、別のことに興味が移っていることも。 - 環境が遊びにくい
おもちゃを広げるスペースがない、親や兄弟がそばにいないと遊びにくい、などの理由で使われなくなる場合もあります。 - 自由度が低い
あらかじめ決められた遊び方しかできず、同じ方法でしか遊べないと、一時したら飽きやすい傾向にあります。 - 存在を忘れている
外から見にくいおもちゃ収納だと、おもちゃ自体の存在を忘れてしまうことも。
年齢が小さいうちは特に、目に入ったものを手に取ることが多いので、置く場所やおもちゃの目立ち度によっても、遊ぶ頻度が変わってきます。
何事もマネから始まる


何かができるようになるためには、スポーツでも仕事でも、なんでも真似からです。子供でも大人でも同じこと。
真似っこが上手な子ほど、上達が早いと言います。
おもちゃを与えるだけでなく、そのおもちゃの使い方を示してあげると、自然と真似して遊び始めることができます。最初は見ているだけでも、子供はしっかり学んでいるので、必ず後々のアウトプットにつながってきます。
上に兄姉がいる子が「何も教えてないのに、いつの間にかできるようになってた!」というのも、上の子を見てインプットしているからです。
最初は誰かが、おもちゃで遊んでいるのを見て、真似をすることから始めても良いのではないでしょうか。それは、親や兄弟、動画でも良いかもしれません。
おもちゃの世界を広げてあげよう


子供にとって、おもちゃの遊び方を覚えることは、一気に世界が広がることにもつながります。
では、子供が遊ばないおもちゃを、楽しく遊べるアイテムに変えるにはどうしたら良いのでしょう?簡単に実践できる方法をご紹介します。
1. 親が一緒に遊んでみる
子供がどう遊んで良いかわからないときは、大人が遊び方を示してあげるのが一番!
例えば、つみき1つにしても、
- 建物や街を作ってみる
- 物や動物に例えて形を組み合わせてみる
- 形別に並べてみる
- ドミノ倒しのように使ってみる
- ひたすら積み重ねてみる
など、何通りもの遊び方ができます。
すると、その中から自分の興味を引く遊び方を見つけて熱中し始めたり、その遊びを発展させたりしていくことができるようになります。
そして何より、親が楽しそうに遊んでいる姿を見ると、子供も興味を持ちやすくなります。
2. おもちゃを別の遊び方で活用する
本来の遊び方にこだわらず、新しい使い方を試してみましょう。
- 積み木:車のコースを作ったり、数字や色の学習に使ったり。
- おままごとの食材:実際のお菓子作りごっこや、お店屋さんごっこに発展させる。
- パズル:完成した後にその絵を使って話題を広げたり、裏面に絵を描いてオリジナルパズルを作ったり。
ただ、「この遊び方は継続して欲しくないな」と思う遊び方は、教えないでおくのがベター。
例えば、おもちゃを楽器代わりにして叩いてみたりすると、それをずっとやられた時に「うるさーい!」とママのストレスになりがち。
遊び方を教えるときは、その後のことも考えておくのが良いでしょう。
3. おもちゃをローテーションする
子供は見慣れたおもちゃには飽きてしまうことがあります。そんなときは、少しおもちゃを「お休み」させるのがおすすめ。
『箱やクローゼットの奥にしまって、数ヶ月後にまた出してみる。』
というのが、とてもオススメなお休み方法。
長い間使っていなかったり、見ていなかったおもちゃは、子供も忘れていることが多く、新しいもののように見えたりします。久々に再開した時に、見向きもしなかったのが嘘のように熱中してくれることもあります。
4. 遊びやすい環境を整える
おもちゃが取り出しにくい場所にあったり、部屋が散らかっていると、遊ぶ気が起きにくくなることもあります。
その対策として、おもちゃを取り出しやすく、遊びやすい環境に整えてあげることが大切です。
- おもちゃをジャンルごとに収納し、取り出しやすくする。
- スペースを広げ、自由に動ける環境を作る。
また大人からすると、散らかっていくのが嫌で、どんどん片付けてしまったり、「1つ出したら1つ片付ける」などのルールにしてしまったりしますが、子供の世界を広げてあげるなら、そこそこの我慢も必要。
子供がおもちゃの引き出しをひっくり返して、全部出してしまったり、数種類のおもちゃを出しっぱなしで遊んだりしても、そこから遊びや想像力が広がる可能性もあります。
「最後には必ずお片付けしようね!」などと決めて、ある程度見守るのも重要です。
5. 子供に”選ばせる”遊びを取り入れる
子供自身が「これで遊びたい」と思えるようにすることも大切。
- 毎朝「今日はどのおもちゃで遊ぶ?」と聞いてみる。
- 好きな組み合わせで自由に使えるようにする。
- おもちゃを自分で選べるように、収納を「見える化」する。
前の項でお伝えしたことと重複する部分もありますが、おもちゃを見やすく、選びやすくすることは、非常に重要です。
子供が「遊ばない」のではなく、ただ単に見えていないだけかもしれません。
実践例:家にあるおもちゃを活用した遊びアイデア
以下は、家庭で簡単に試せるおもちゃの活用方法です。
おもちゃの遊び方は一つじゃないということを教えたり、親にとっても遊び方を学ぶ機会になるので、どんどん試してみてください。
- ぬいぐるみ:お医者さんごっこや学校ごっこをして、お世話遊びを広げる。
- クレヨンと紙:お絵かきの後に、他のおもちゃを組み合わせて「世界地図」や「冒険マップ」を作成。
- ダンボール箱:おままごとおもちゃも使ってお店屋さんごっこや秘密基地を作る。
これらの方法は特別な準備がいらず、すぐに始められるものばかりです。
他のおもちゃと組み合わせて、遊びを発展していくと、さらに世界観が広げられます。
うちでよくやるのは、木製レールなどで線路を作って、積み木で建物やトンネルを作ります。そして、たまに怪獣(主に下の子。笑)が街を壊しにきては、戦いごっこが始まります。
色々なおもちゃを一緒に使ったり、様々な遊び方をすることで、おもちゃ自体を飽きにくくなります。
まとめ


子供が遊ばないおもちゃを前に、つい「せっかく買ったのに…」と思ってしまうこともあるかもしれません。でも、そのおもちゃにはまだたくさんの可能性が眠っています。
大人が少し工夫して遊び方を広げてあげれば、子供にとって新たな世界が広がります。家族みんなで楽しめる遊びを通じて、おもちゃをもっと活用してみましょう!
ちなみに、こんなリスクをそもそも減らしたい方は、おもちゃサブスクの検討もおすすめですよ。
おもちゃで遊ぶ時期は、本当にあっという間に終わってしまいます。おもちゃを通じて、お子さんと一緒に楽しい時間を過ごしてくださいね。
















